共にできるを、ふやす。デフと聴者の関わり方をアップデートする「サイレントボイス」
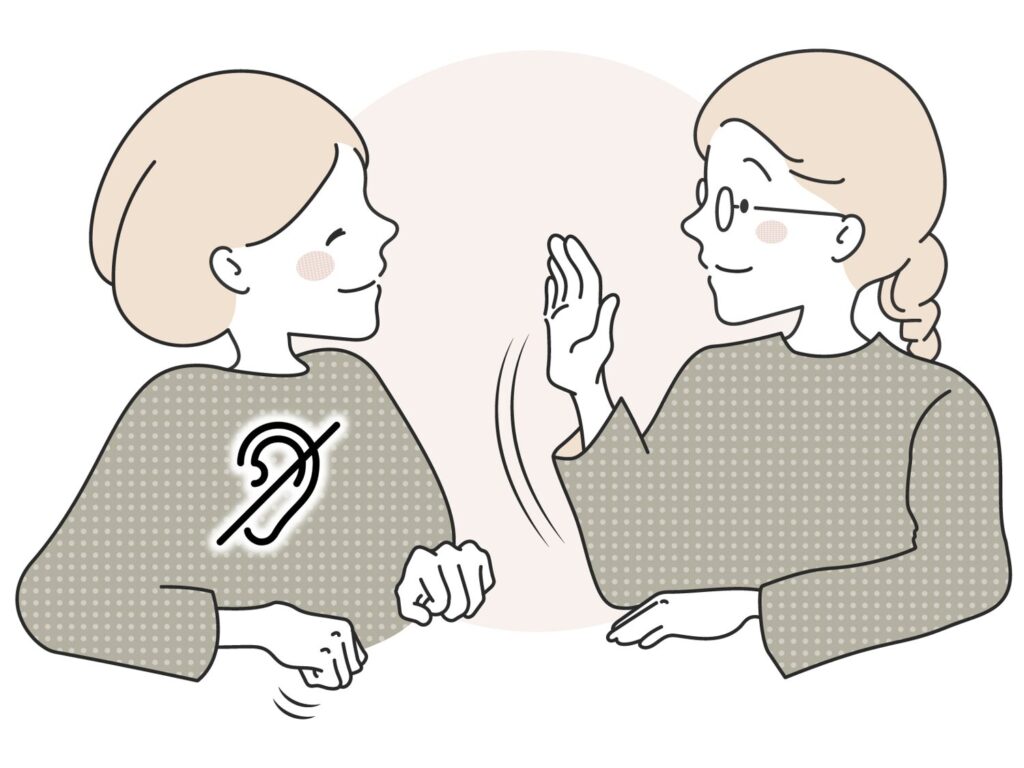
皆様、こんにちは。
伝えたいことが伝わらない…どうしてわかってくれないの! 皆様もそんな悲しさや憤りを経験したことはありませんか?通信技術が発達し、SNSなどの便利なツールが普及した現代でさえ、私たちのコミュニケーションに関する悩みは尽きません。しかし、世の中には、この悩みを慢性的に抱えている人たちがいます。難聴者・ろう者(または、デフ)と呼ばれる人たちです。厚生労働省の調査結果によると、現在、日本には聴覚に困難を抱える人たちは約1,430万人いるとされています。また、先天性の難聴児は1,000人に1~2人の割合で生まれています。これは決して少ない人数ではありません。
そこで今回は、聴覚に困難を抱える子どもたちに特化した教育支援サービスを提供しているNPO法人「サイレントボイス」さんについてお話ししたいと思います。この記事を読んでくださった皆様が、難聴者・ろう者の抱える悩みに気づき、寄り添い、彼ら彼女らが自分らしく生きられる社会に少しでも関心を持って頂けたら嬉しいです。

2016年12月の設立より、聞こえない、聞こえにくいなど聴覚に困難を抱える子どもたちへの教育支援を行っているNPO法人です。大阪市内で運営している難聴児・ろう児のための学習塾「デフアカデミー」や、全国の子どもたちを繋ぐプラットフォーム「サークルオ―」でのコミュニケーション支援等を通して、デフと聴者の「共にできる」を増やし続けています。子どもたちがコミュニケーションを諦めなくていいように、細部にまで「見て、わかる」を意識した設計がなされています。
=ミッション1=
伝わるを、ふやす。
=ミッション2=
社会へ、ふやす。
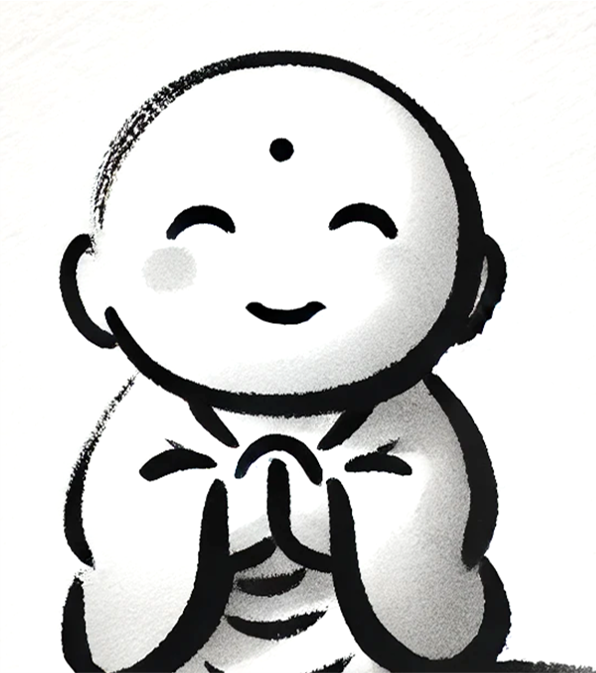
ビジネスとして立ち上がらない領域にこそ課題が残っています。だからこそ、ビジネス以外の方法で、解決に向けたアプローチが必要なのです。

2. 日本における聴覚障害の現状
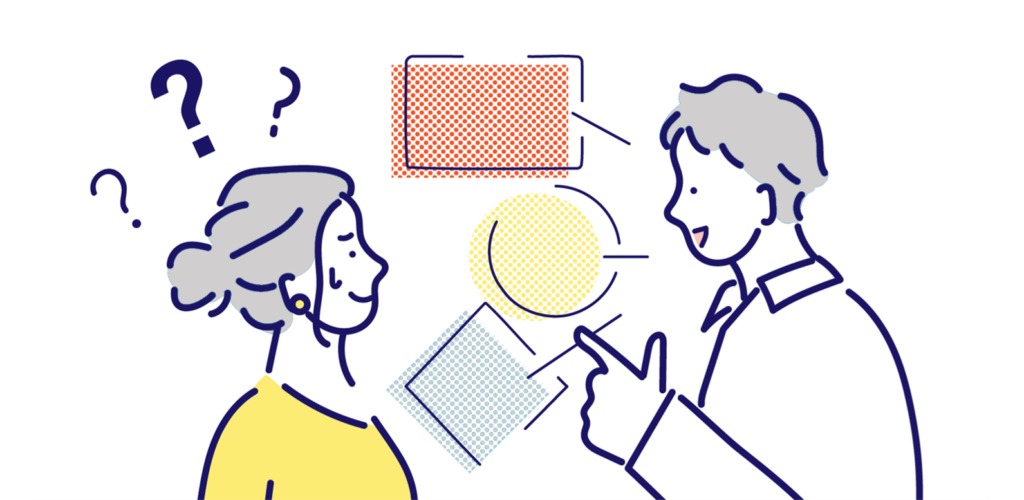
2-1. 聴覚障害者の人口

厚生労働省「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」によると、日本には聴覚・言語障害を持つ方が約38万人います。加齢などが原因で、日常生活で聞こえにくさを感じている人たちを含めれば、その数は1,400万人以上に昇ります。これは日本の全人口の11.4%にあたります。
また、先天性の難聴児は1,000人に1~2人の割合で生まれていますが、その遺伝的な要因は分かっていません。両親共に聴覚障害がないにも関わらず、子どもが難聴児であったケースがほとんどです。その逆も然りで、聴覚障害を持つ両親から、普通に耳が聞こえる子どもが生まれることもあります。
2-2. 聴覚障害のグラデーション
一口に聴覚障害といっても、聞こえの程度や育ってきた環境によって異なってきます。耳栓をしているように音が聞こえにくいという軽い症状のものから、全く聞こえないという重度のものまで様々です。また、聴覚障害を先天的に持っている場合もあれば、病気や加齢などにより後天的に発症・進行した場合もあります。それぞれの方が、日常の中でそれぞれ違ったコミュニケーションの課題を抱えています。
2-3. コミュニケーションの壁
耳の聞こえない人のコミュニケーション手段として「手話」をイメージされる方が多いと思います。しかし、実際に手話を使える人・使っている人は、全体の約18%と意外に少なく、手話ができない方が多いのです。補聴器によるサポートや筆談、読唇、指文字など、聴覚障害者の中でもコミュニケーション方法の得意・不得意があるのです。

聞こえない、聞こえにくいことでコミュニケーションにズレが生じてしまう…それだけで、考える力がないと思われてしまうこともあります。また、聞き取れなかった問題には「わかったふり」をして笑顔でやり過ごすこともあり、成功体験や自己肯定感を得にくいという傾向もあります。たとえ本人に頑張りたいという意志や能力があっても、成長できる機会や活躍できる環境が少ないのが現状です。
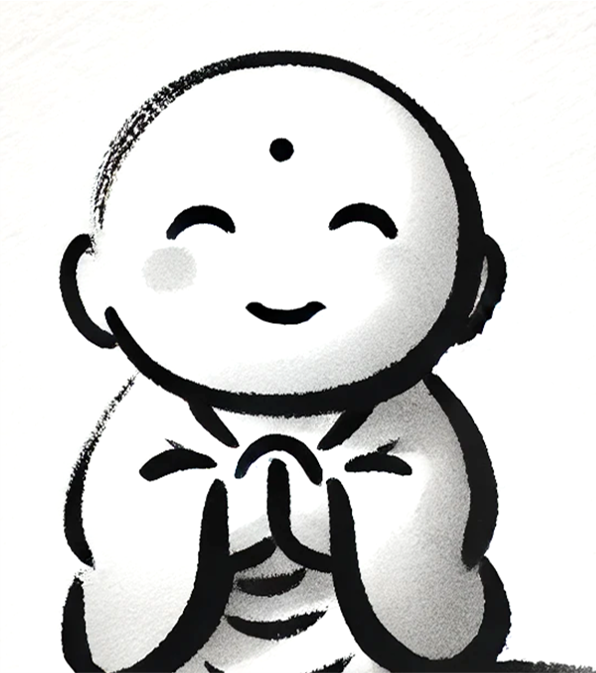
聴覚障害を持つ子どもたちは、児童発達支援センターや特別支援学校(ろう学校)、病院などで教育を受けますが、そのような施設も専門性を持った職員も圧倒的に足りていません。

普通の学校に通っている場合もあるけれど、「学校の中で自分1人だけ聞こえない子ども」であることで、孤立を感じているんだ。
3.「サイレントボイス」の取り組み
聞こえない、聞こえにくい子どもたちは、コミュニケーションなどの問題から孤立しがちです。身近に同じ境遇の子どもがいないことで、世界で自分だけが音のない世界に生きていると考える子どもたちさえいます。NPO法人サイレントボイスさんは、そんな聴覚に困難を抱える子どもたち(難聴児、ろう児)に特化した教育支援サービスを提供しています。
➀ 難聴児・ろう児のための学習塾「デフアカデミー」

「できないこと」の理由は、決して「聞こえないこと」だけではありません。難聴児・ろう児は、周りから結果や目的だけを伝えられることが多く、考えるプロセスを学ぶ機会が乏しい傾向にあります。そんな子どもたちのために、サイレントボイスさんは、大阪市内にて、ろう児・難聴児に特化した放課後デイサービス「デフアカデミー」を開設・運営しています。
聴覚支援学校や難聴学級の小・中・高校生を対象に、「見て、わかる」を意識した集団授業やイベントを開催しながら、子どもたちがコミュニケーションの壁を越えて「やりたいこと」を叶えていくための成長の場を提供されています。また、デフアカデミーのスタッフさんは、子どもたち1人ひとりと向き合い、「伝えたいこと」が相手に伝わるまでとことん付き合います。伝え方が分からないときは、一緒になって考えてくれます。子どもたちがコミュニケーションを諦めなくていい、そんな居場所づくりを心掛けています。
② オンライン対話授業「サークルオー」
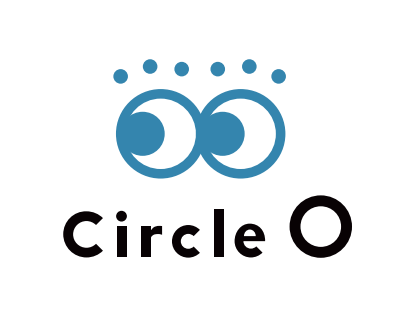
サイレントボイスさんは、全国を対象にした「サークルオ―」というオンライン教育プラットフォームも用意しています。孤立しがちな地域のろう児・難聴児に、オンラインでの出会いや学び・体験の場を提供することにより、彼ら彼女らの「やってみたい」という意欲を高めることを目的に活動されています。手話はもちろん、写真や映像などの視覚的教材を通して、子どもたちの「わかる」「伝わる」「できる」を育んでいます。

耳の聞こえる先生も聞こえない先生も同じくらい在籍しているから、生徒のコミュニケーション方法や性格、学びたいことなどにあわせて先生をマッチングしてるんだ。
4. 結び
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
私たちヒトは、良くも悪くも差別をする生きものです。しかし、たとえ言語や考え方に違いがあったとしても、お互いの共通点がたった1つ見つかるだけで親密さを感じる生きものでもあります。耳が聞こえる、聞こえないという違いだけで、コミュニケーションを諦めてはなりません。お互いに、理解する努力、伝えたいことを伝える努力を怠ってはならないのです。NPO法人「サイレントボイス」さんは、そんな聴覚に困難を抱える子どもたちが、助けられるだけの存在ではなく、自分らしい人生を歩んでいける教育を提供されています。今の時代だからこそできるコミュニケーション支援で、デフと聴者の「共にできるを」を増やしています。AIが発達・普及していく。これからの社会では、こういった取り組みや姿勢が、なおさら大切になるのだと私は思います。
自分に優しく、人に優しく。自分貢献から他者貢献、そして、社会貢献へ。それが回りまわって、皆様自身や家族にとって優しい社会になるのだと、私は信じています。







